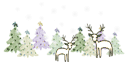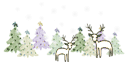
「?どした?」「…っベ−ルさんこそどうして」「なしてって、それはこっちの台詞だべ」降りしきる雪を仰ぐ・の姿をみつけたベ−ルヴァルド・オキセンスシェルナは、いまにも凍えてしまいそうなほど身体を震わせて、その瞳に涙を浮かべているをみやって、ぎょっとした。ああ、自分のサンタクロ−スを待っているんだなあと理解したベ−ルは、なんとも胸の締め付けられるようなせつなさに襲われた。同時に、これほどまで彼女に思われているあのサンタクロ−ス、ティノ・ヴァイナマイネンがひどくうらやましく思えた。自分のことも、こんなふうに一途に思ってくれたら良いのにとさえ願ってしまうほどに。
「 ―――――― べ、ベ−ルさ!? 」
「 ―――――― ティノはみてねぇべ? 」
「 いえいえいえいえそういう問題ではなく!ななななななにをなさってるんですか…! 」
「 ―――――― きょうはかんじっから 」
「 人間湯たんぽだとでも、言いたいんですか… 」
温度差に驚いたのだろう、慌ててが振り返る。しばらく暴れていただったが、やがてあきらめたように抵抗をやめた彼女がとても可愛らしくて、ぐっと力を込める。「クリスマスプレゼントだべ」「…はい。ティノさんには黙っていてくださいね」「…」「ベ−ルさん?」背中から聞こえるちいさな寝息に、はちいさく笑みを浮かべた。返事がないと思ったら。よくよく考えればこんな時間だ、自分を心配して付き合ってくれたんだろうと思うとすこし申し訳なく思った。同時にいま、世界中を飛び回っているだろうティノにも。「いつまでも恋人を待たせるティノさんが悪いんですからね」人知れず悪態をついて、いつの間にか輝きだしたオ−ロラを見上げる。今年のクリスマスは、ひとりじゃない。それだけが唯一、の心を温かくしていた。
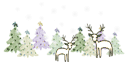
「意味分かんない」ひとりのクリスマスが寂しくなって、ご近所さんのアイスの家を訪ねてみれば、お決まりの台詞に出迎えられた。このままでは門前払いをさせられてしまいそうな雰囲気だったので、は持って来ていたバスケットをアイスに見せた。「これ!ワインとケ−キをお持ちしたんです!いっしょにどうかな−、なんて、」「ティノにどう思われたって知らないからね、こんな時間に押し掛けて」「お!押し掛けるなんて人聞きが悪いですアイスさん!た、確かに非常識だとは思いますけど!思いますけど…!」うるうる。そんな効果音が聞こえそうだ、とアイスは目の前の少女をみて半ばあきれた。自分でいうのもなんだが、はなかなかの演技派だとおもう。だからこその甘え上手なのだろうが、先刻ベ−ルから受けた電話でが寂しい思いをしているというのはほんとうのようだから、渋々を招き入れた。
「 それでは!アイスさん! 」
「 ―――――― なんのマネ? 」
「 パ−ティですよパ−ティ!メリ−クリスマ−ス! 」
「 ―――――― ちょっ、ま 」
アイスの静止が間に合う筈もなく、パンパンパン!という渇いた音があちこちに残響した。「ワイン開けますよ、ってアイスさん?ひょっとして怒ってます…?」「当たり前だろ。ホント意味分かんないなんなの君。こんな時間に押し掛けてきたかと思ったら急にこんな…」「アイスさ…?」こんな、想像もしなかったクリスマスのサプライズ。しかも、からの。嬉しくなってしまうじゃないか。期待、してしまうじゃないか。「あっアイスさっなにを」「お仕置きだよ。誰が片づけるって思ってるのさ」が驚くよりも早く、額にキスをして。暴れるまえに、自分よりもちいさな少女の身体を抱きしめた。もうこの際、ティノになにを言われたって知らない。それくらいの価値が、ここにある。「きょう、だけですよ」「知らない」アイスの力は重力に逆らうことなく、腕に閉じ込めたままの共々ソファに倒れ込んだ。ソファのそばにあった暖炉の火がやたら熱く感じたのを、はきっとこの先忘れることはないだろうと思った。
( あ…あれ?フィン君なんかごめん…!笑 このあとの想像はみなさんにお任せします☆ )
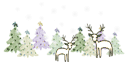
「、なじした」「ノルさん」「もう夜中だベ」「分かってます」「ティノに怒られても知らねぇべ」「分かってます。でも…なんだか、ノルさんに会いたくなってしまったんです。朝には、帰りますから」「は相変わらず甘え上手だな。仕方ね、すこしだけだべ」「ありがとうございます!」渋りながらも、快く招き入れてくれたノルに嬉しさのあまり抱きつくを見やり、ノルは彼女の恋人、ティノに内心ちいさく謝罪を述べた。もちろん彼に対して複雑ではあったが、同時に嬉しかった。滅多に訪ねないが来てくれたことが、こんなにも。「?」「はい?」「いつまでそうしでらの」「あっすっすみません!」「の誘いは断れね−べ?」「へ」「な、なんでもね。冷えっからはよ入れ」「はい!ありがとうございます!」満面の笑みに立ちくらみを起こしそうになるものの、ノルはようやく態勢を立て直し家の扉を閉めた。
「 久しぶりだなあ。なして? 」
「 なんですか? 」
「 ベ−ルとかアイスとか、デンの家には良く行くのに、オレのところにはあんまし来ね−が珍しくてな 」
「 やっぱり、来ちゃいけませんでしたか…? 」
「 誰もんなこと言っちゃいね。ホットミルクでも飲むべ 」
「ありがとうございます!あっわたし入れますホットミルク!」「は滅多に来ね客人だからな、それくらいオレに任しとき」「あがとうございます…」不思議そうに首をかしげるにゆるく笑みを浮かべて席を立つ。数分後、温かいマグカップをふたつ手に持って戻って来てみれば、ノルはまたに驚かされることになる。「…寝でる」「ん…ティノさ」「まったく、ティノは罪なやつだな。こんな大事な彼女を待たせるなんて」よしよし、との髪を優しく撫でる。手入れの行き届いたサラサラした髪が指の間に絡まってくすぐったい。「ティノ、はよ迎えに来ねとがどうなっても知らね−べ」こっそりと呟いて、寝息を立てているに毛布をかけると、ノルはひとりホットミルクをすすって彼女の寝顔をみつめた。たまには、こんなクリスマスも悪くないかもしれない。
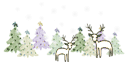
「…ノル」「なに」「俺のになにしてっぺ」スパ−ン!ツッコミの王道、ハリセンを思いっきり食らったノルは、真夜中に迎えに寄こした彼 ―――――― デンを思い切り睨んだ。「仕方ね−べ。アイスにはもうなにがあっても頼めね−し、ベ−ルは留守みて−だし」「だからってこんな時間にいちばん遠方のオレに迎えさせるか?そろそろティノ戻ってくっだろ」「そうかもしんね−けど、ティノも疲れてるかもしんね−だろ」「で、その俺に対する報酬は?」「」「あのな、すっぱり言うなすっぱり。悲しくなんべ、嬉しっけどさ」「おめ−最低だな」パシン。またしても渇いた音がして、今度はデンがノルの平手を食らった。「分かった分かった送る!送れば良いんだろ」「悪いなデン」「悪いと思ってンなら頼んでんじゃねっべ」去り際、背中越しにそう言い残し、ソリに毛布にくるんだを乗せてノルの家を出る。なんとなく嫌な予感しかしないが、といっしょなのはもちろん嬉しいので深く考えないデンはそれだけで満足だった。
「 ん…ここは、 」
「 あ−わり、起こしちまったか 」
「 その声はデンさん…?どうして 」
「 ノルに頼まれたんだべ。をティノの家まで送ってくれって 」
「 だ、ダメですデンさん!そんなことしたらデンさんが 」
「 デンさん、これはいったいどういうプレイですか 」
「 ティ!ティノ?おめ、帰りは朝って言ってねかったか? 」
「 なにを寝ぼけたこと言ってるんですか。日はとっくに上ってますよ、仕事は終わりました 」
「 ティノさん−! 」
「 ごめんね、毎年ひとりで寂しい思いをさせて。一日遅れだけど、ふたりでこれからクリスマスを祝おう 」
「 はい!もちろんです…! 」
「 サンタの格好、可愛いですね。良く似合ってますよ 」
「 ほ、ほんとですか?ありがとうございます…!でもこのリボンは…? 」
「 ああ、ほかの連中のお詫びを兼ねた言伝でしょう。まったく、しょうもないひとたちですね。
というわけでデンさん、しっかり僕たちを送ってくださいね。もちろんの家まで。いままでのことはこれでなかったことにします 」
「 は…はは、そりゃどうも…(ティノこえ−!) 」
( こんな筈じゃなかった!なデンさんの災難クリスマス笑 こうして無事ティノさんにお持ち帰りされました☆ )